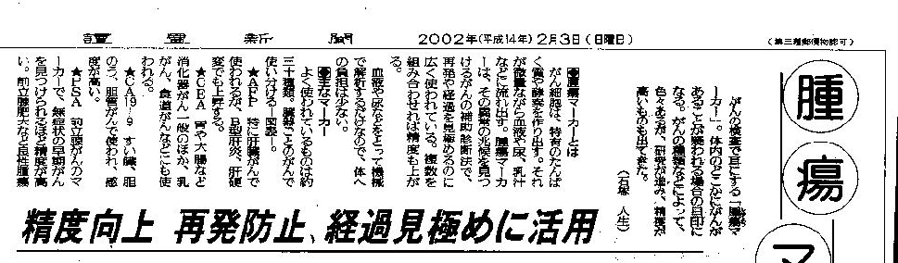
腫瘍マーカー がん部位チェック
読売新聞 平成14年(2002)2月3日記事より![]()
◆精度向上 再発防止、経過見極めに活用
がんの検査で耳にする「腫瘍(しゅよう)マーカー」。体内のどこかにがんがあることが疑われる場合の目印になる。がんの種類などによって、色々あるが、研究が進み、精度が高いものも出てきた。(石塚 人生)
◆腫瘍マーカーとは
がん細胞は、特有のたんぱく質や酵素を作り出す。それが微量ながら血液や尿、乳汁などに流れ出す。腫瘍マーカーは、その異常の兆候を見つけるがんの補助診断法で、再発や経過を見極めるのに広く使われている。複数を組み合わせれば精度も上がる。血液や尿などをとって機械で解析するだけなので、体への負担は少ない。
◆主なマーカー
よく使われているものは約30種類。臓器ごとのがんで使い分ける=図表=。
★AFP 特に肝臓がんで使われるが、B型肝炎、肝硬変でも上昇する。
★CEA 胃や大腸など消化器がん一般のほか、乳がん、食道がんなどにも使われる。
★CA19―9 すい臓、胆のう、胆管がんで使われ、感度が高い。
★PSA 前立腺がんのマーカーで、無症状の早期がんを見つけられるほど精度が高い。前立腺肥大など良性腫瘍でも高値になる。

◆標的は遺伝子
がん遺伝子が作るたんぱく質を標的にした新しい「DNA(デオキシリボ核酸)マーカー」も出始めている。乳がん患者のうち、2―3割が持つ特殊な遺伝子増幅を突き止めるマーカーがその1つだ。従来より精度が高く、再発時の陽性を示す割合も9割と高い。早ければ、今春にも保険適用が認められそうだ。この遺伝子を標的にした抗がん剤が「ハーセプチン」(成分名トラスツズマブ)で昨春保険適用された。
◆マーカーの限界
栃木県立がんセンター研究所室長の菅野(すがの)康吉さんは「マーカーはがんを追跡する簡便な方法だが、万能ではない」と話す。現在のマーカーでは、数値上問題はなくても、がんが進んでいる場合がある。また高齢者向けの定期検診でも、がんが見つかるのは1000人に1人に過ぎず、健康診断などでとった血液すべてをマーカーで調べるのはばく大な費用がかかるため、行われていない。全身のどこにがんがあるかを見つけるのも、マーカーのみでは難しい。だが、例えば肝炎ウイルスを持つなど、肝臓がんになる危険度が高い人のマーカーを追跡していけば、早期治療につながる可能性は高い。菅野さんは「遺伝子レベルの異常を見つけるマーカーの開発は始まったばかり。マーカーだけでは分からないことも多く、1度がんになった人は、定期的な検査を欠かさず受けることがより重要だ」と話している。